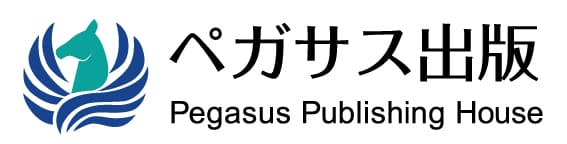【大人の小論文2】ブログは論理的に書けば共感を得られやすくなる



「小論文」は、自分の意見を論理的に述べるものでした。「論理的」とは、国語辞典を引くと、「論理にかなっているさま。きちんと筋道を立てて考えるさま。」と書かれています。つまり、言葉を変えると、論理的とは、「テーマに対する背景や意見、理由、根拠を明確にして、わかりやすく」ということになります。
目次
ブログの書き方:ブログの目的は「共感」を得ること
ブログの記事で求められるのは、読者に「共感」を与えることです。
読者から「共感」を得るには、最初から最後まで文章を読んでもらって、理解してもらわなければなりません。
そこに行き着くには、論理的に文章を書くことが求められるということですね。
では、具体的にどのように書けばいいのでしょうか?
はい、ここで、小論文を書く時の、
「序論」→「本論」→「結論」の流れが役立つのです。これを応用していきます。
小論文は、自分の意見を述べるために、最初に、「序論」で「自分の意見はこうだ。これからこういうことを話すよ」と読者に喚起しました。
そして、「本論」では、自分の意見を裏付ける理由を述べました。
最後の「結論」では、「だから~なんだよ」ともう一度、序論で述べたことと同じことを述べました。
ブログでも形は同じで、最初と最後の部分は同じことを述べます。
ただし、この流れは、ブログでは、読者に訴求することが求められるので、次のような形に変わります。
「(序論)読者の注意を引く」→
「(本論)一番言いたいことを述べる」→
「(結論)念押し」
と考えるとわかりやすいでしょう。
「誰に」「何を」伝えるかを明確にする
ブログのタイトル
まず、これから、書こうとするブログの内容に対するタイトルをおおまかに決めましょう。ここは、テーマをずらさないためにも、まず書いたほうが良いでしょう。
ここでは、仮に、「情報発信があなたの成長をうながす」をタイトルとします。
ここで、大切なのは、このタイトルに対する内容で、「誰に」、「何を」伝えるかです。
ここを絞り込むことで、文章が書きやすくなります。
ブログで「誰に」「何を」伝えるか
ここでは、次のようにします。
【誰に】・・・普段、自分の言いたいことがうまく言葉に表現できないかた。
【何を】・・・まずは、書くことを少しずつ始めていこう。小論文の流れで、短い文章を書くことを練習していこう。
ちなみに、小論文の場合は、あまりターゲットを意識しません。基本、ターゲットは「試験官」など、評価する人がターゲットになります。
それよりも、だれが読んでもあなたの意見を正確に理解できるように書くことが求められるのが小論文です。
ブログの書き方:(序論)「注意を引く」
ブログの場合、小論文の「序」の部分で、読者を注意を引くことが大切です。
小論文のような試験と違って、ブログは、「興味がある人しか読まない」わけですから、ブログのタイトルにした内容を述べていくにあたって、まずは、読者が「お?」と気を止めるような出だしで書き始めないと読んでもらえません。
ただ,ここで、不特定多数の人に読んでもらおうと考えないことです。「誰に」でイメージしている人たちが読むためのもの、と絞り込んでください。こうすることで、ターゲットではない人が読んでも、意味が通じるものであれば、人は確認の意味で読むからです。
慣れないうちは、最初を疑問系にすると良いでしょう。
「あなたは~について知っていますか?」や、
「あなたは、~について悩んでいませんか?」
というように、疑問系にすることに、そこに何かしらの共通点を見出した人は次を読もうとするはずです。
たとえば、タイトルが、上記のように、「情報発信があなたの成長をうながす」というようになっっていたら、
まず、「あなたは、日頃からブログやSNSなどで情報発信をされていますか?」という感じで始めることができます。
あるいは、「あなたは普段、自分が言いたいことが言葉にできずに苦労していませんか?」でも良いかもしれません。
目的は、「誰に」で想像した相手が、「話を聞かなくちゃ、聞いてみたい」という思いを抱かせることです。
最初に質問したら、続けて、少し現状を述べていきましょう。
このとき、読者に対して味方になったつもりで書くと良いでしょう。こうすることで、「序」の部分に少し厚みがでました。
「あなたは、日頃からブログやSNSなどで情報発信をされていますか?」
「すでにされているのならば、ある程度文章を書くことは苦痛でないと考えますが、普段されていない人にとっては、文章を書くのが苦手だからという理由で書くことを敬遠してしまっているかもしれません。しかし、文章を書くことは、あなたの成長をものすごく手助けしてくれます。書くことを習慣にしていくと、自己成長が著しくなるはずです。」
情報発信している人にとっては、ちょっとうれしい言葉です。情報発信していない人には、情報発信していくと良いことがあるのかも?と期待を持たせることができます。
ブログの書き方:(本論)一番言いたいことを述べる
さて、「序」の部分を述べたら、いよいよ「本論」に入ります。前の文章からの流れで、話がつながるように書き始めます。
「実は、この話は、脳科学の観点からも言われていることです。人は、自分の頭の中を、書いてアウトプットすることで、脳が活性化するのだそうです。そこに、フィードバックを加えると、アウトプットしたことを振り返ることができ、さらに、脳が活性化。この活性化を繰り返すことで、脳の働きがよくなっていきます。すると、普段、なかなか自分の気持ちを表現できなのも、少しずつ言葉にできるようになっていきます。
このようにして、自分の気持ちを言葉にすることに慣れてくると、文章も書けるようになってきます。
おそらく、「文章が苦手」と言う方は、書く前の「何を書こう」という思考をうまく言葉にできないからなのだと思います。文章が不慣れであっても、短い言葉でいいのでアウトプットを繰り返していくことで、苦手意識は減っていくことでしょう。
アウトプットで訓練して、自分の思考を表現できるようになれば、当然、普段の言動も周囲との関係にも会話による変化は出てきます。今まで、自分の言いたいことが言葉にできなかったことができるようになることで、あなたは自己成長し、人生を変化させていくきっかけにもなるのです。
(中略)
本論も、書きたいことがまとまっていないと悩ましいかもしれません。ただ、難しく考えないでください。
ここでたくさん書こうとするから悩ましいのであって、ブログのタイトルどおりに、言いたいことだけを絞り込んで書くようにすれば、それほど難しくはありません。
本論の文章で途中悩む場合は、たいだい、書いているうちに言いたいことがあれもこれもと出てきてしまい、タイトルを忘れて、話を脱線させてしまうときです。
もし、書いているうちに他にも書きたいことが出てきたら、それはメモをして次の記事として書いていくようにすると良いでしょう。
とにかく、本論は、タイトルで言いたいことに絞り込んでいきましょう。
ブログの書き方:(結論)念押し
結論は、「序」の部分で伝えた内容を、もう一度伝えます。そのまま同じ文章を書くのではなく、違う言葉で表現するようにします。
たとえば、この場合ならば、次のようにまとめることができます。
「このように、アウトプットをすることで、脳を活性化することができます。少し慣れてきたら、まずは、FacebookやTwitterなどで情報を発信するのもおすすめです。
また、ブログを始めても良いでしょう。
さらに、これから仕事のためにブログを書かなければならない方は、自身の仕事の内容に特化して、定期的にブログを書くように習慣付けていくと良いでしょう。ブログを続けることで、自分自身の仕事に対する考えも明確になります。また、人と話をするときも、普段から頭の中を書くことで整理されるので、余裕が出てくるはずです。このような相乗効果が、さらにあなたを成長させてくれるはずです。
さあ、今日からアウトプットを初めて、どんどん成長し、人生を向上させていきましょう。」
このように、最初に述べていることとは文章は違いますが、まとめとして、「序」で言っていることをもう一度最後に言うことで、相手に、記事の内容を「確認」という形で納得させることができます。
サンプルを読み返してみるとわかるのですが、「本論」の部分だけが書いてある記事があたっとしたら、どう感じるでしょうか?
書いてあることは理解ができたとしても、印象には残りにくいものです。これだけ読んだら、「で?」と聞き返したくなります。
この「で?」と読者が感じてしまっては、共感を得られないということです。
だから、「序論」と「結論」で、「これから伝えますよ」と、「こうなのですよ。わかってもらえましたか」と付け加えることで、読者は共感しやすくなるのです。
ブログ記事だけでなく、本を書く際にも応用できる型
余談ですが、文章の展開方法は、これだけでなくいろいろありますが、この型を知っておけば、ブログのみならず、本を書く時にも有効です。
本は、ページ数が多くても、実用書では、章や項が多くなります。たとえば、1章ならば、1-1,1-2、1-3とそれぞれ見出しが付き、項ごとに2~4ページ程度でまとめていくことがよくあります。この項で書く内容は、まさに、この展開方法でほとんど書けるはずです。
いわば、本は、企画や全体構成はもちろん大切ですが、分割すると、小さな記事を寄せ集めてでもあります。
だから、この型で、コンパクトに述べられる練習をすることは、文章上達にもつながりますね。
まずは、短い文章から始めれば良いので、気になった方は、今日から書いてみてください。
投稿者プロフィール

-
マーケティング出版コンサルタント 環木琉美(たまきるみ)
ペガサス出版代表
2013年より電子書籍出版サービスを開始し、特に本の執筆支援を得意とする。テクニカルライターとして過去に商業出版で総部数60万部を出版。豊富な出版経験を活かして、現在は、起業家や小さな会社向けにターゲットを絞り、販売促進の本を提案している。情報化時代の信用・信頼につながる本を、ブログを書くように普通に皆が書けるようになる時代が来ることを願っている。
最新の投稿
 文章の書き方2019.07.23文章が正しく書けていなくてもメッセージは伝わる
文章の書き方2019.07.23文章が正しく書けていなくてもメッセージは伝わる 文章の書き方2019.04.26令和時代の表現のあり方とは
文章の書き方2019.04.26令和時代の表現のあり方とは メディアへのアプローチ2019.04.16Google AdSenseの審査2019年度版に通った話2
メディアへのアプローチ2019.04.16Google AdSenseの審査2019年度版に通った話2 お役立ち本2019.04.09【おすすめ本】売れ続ける理由ー一回のお客を一生の顧客にする非常識な経営法ー/佐藤啓二著
お役立ち本2019.04.09【おすすめ本】売れ続ける理由ー一回のお客を一生の顧客にする非常識な経営法ー/佐藤啓二著